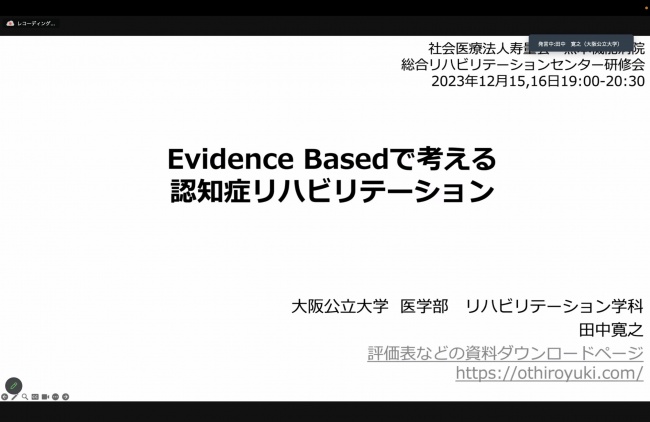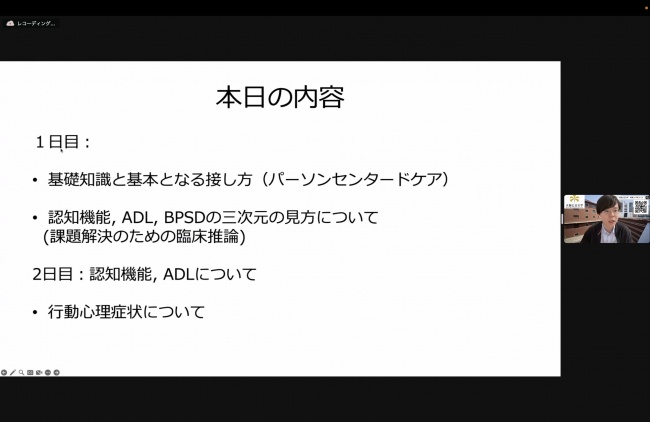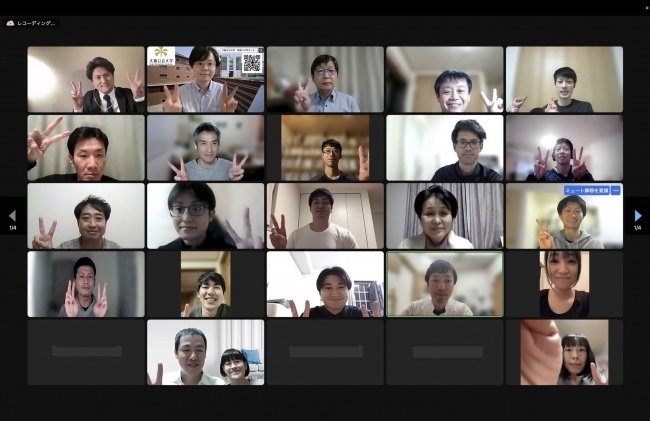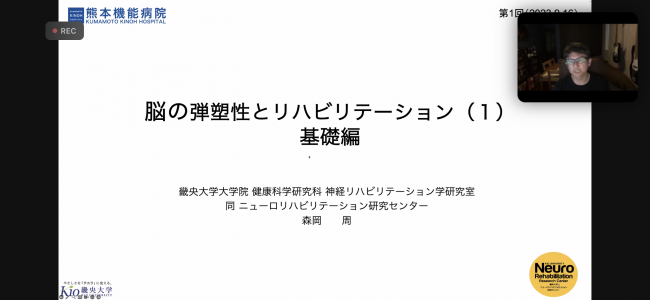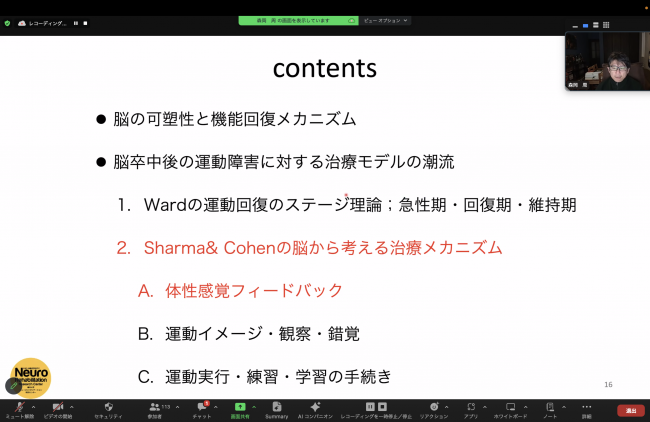熊本機能病院、成尾整形外科病院、東京整形外科ひざ・こかんせつクリニックの認定理学療法士を講師に迎え、専門的で実践的な研修会となっています。
対面研修会では実技講習を交えて、明日からの臨床に役立つ内容となっております。
是非多くの皆様のご参加をお待ちしております。参加ご希望の方は、下記要綱をご確認の上お申し込み下さい。
お申し込みは募集要項のURLもしくはQRコードからお願いいたします。
【日程】
オンライン :①2025年10月5日(日曜)、②11月1日(土曜)、③2日(日曜)
対面 :④2025年12月6日午後(土曜)、⑤12月7日午前(日曜)
【時間】①~③9:00~17:50、④13:00~17:50、⑤9:00~12:10
【形式】オンライン(LIVE配信)および対面研修
【定員】15名(定員になり次第締め切ります)
【受講費】 25,000円
【受講対象】登録理学療法士を取得されている方
【申し込み締め切り】2025年9月14日(日曜)*定員になり次第締め切ります
受講スケジュール
募集要項
お問い合わせ先:熊本機能病院 総合リハビリテーション部 理学療法課
担当:今屋将美
E-mail:imayamasami@yahoo.co.jp
電話:096-345-8111(代表)内線1856(外来リハビリテーション室)